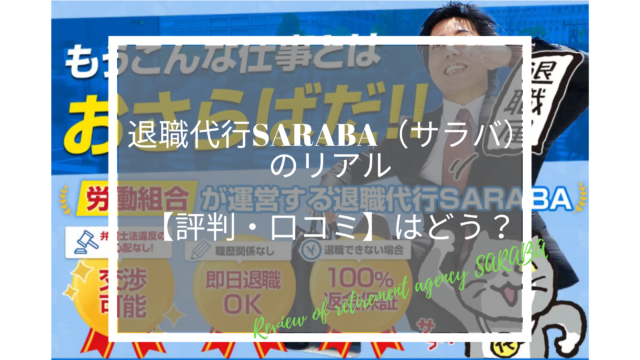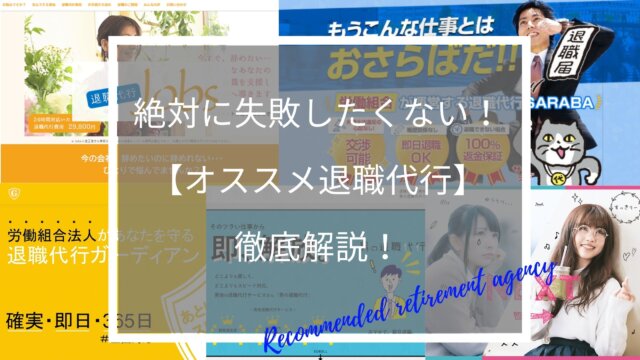【退職代行サービスの法律・就業規則・違法性】退職時の法律と働く人の職業選択の自由について、くわしく解説
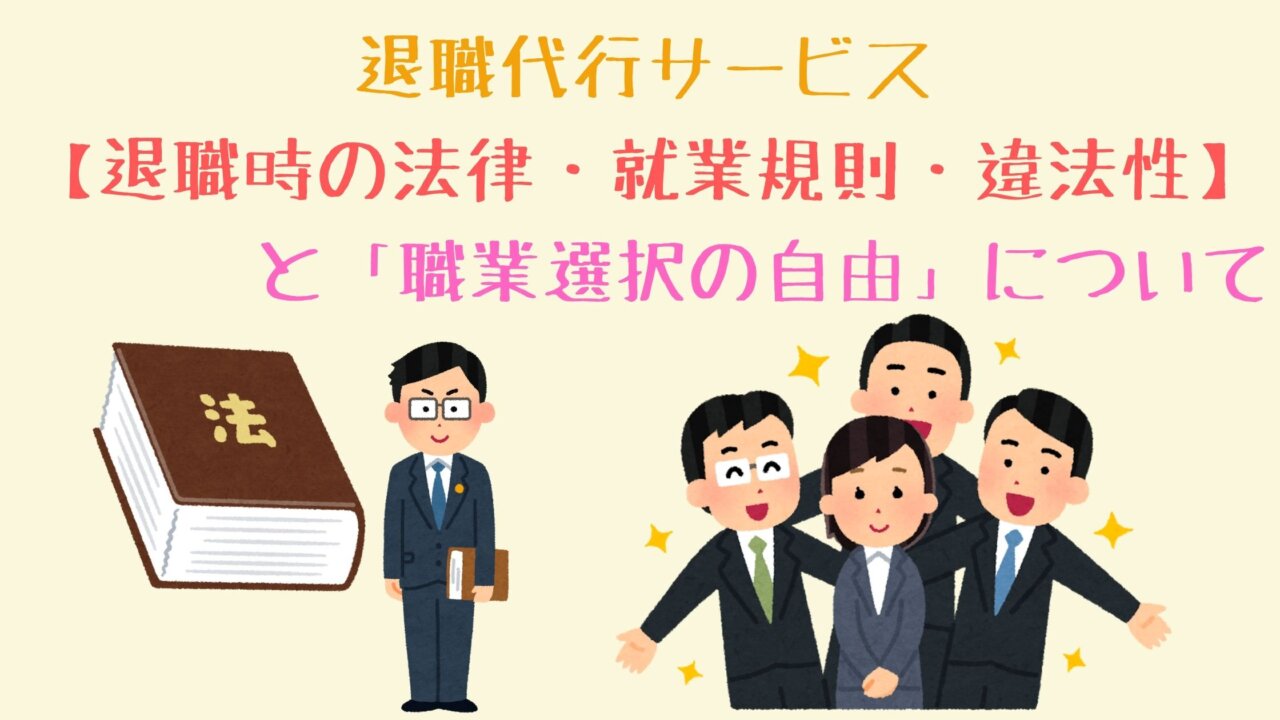
退職代行SARABA

- LINE相談可
- 即日退職可
- 労働組合運営
- 「一般の退職代行」と違って、会社と交渉可
- 万が一、退職できなければ返金保証付きで安心
- 24時間365日いつでも無料相談OK
- メディア掲載多数
- 特典1:行政書士監修 退職届プレゼント
- 特典2:成功率98%・有給消化サポートあり
- 無料転職サポート付
- 退職成功率ほぼ100%
- 料金:一律24.000円
\料金:一律24.000円!返金保証付で安心!/

【即活用できる!即日退職!】
<退職代行17社 徹底比較表!>
※スマホは横画面でご覧ください。
| サービス | 価格(税込) | 運営法人 | 特徴 | |
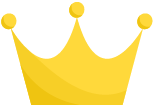  退職代行 退職代行SARABA | 24.000円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・累計利用者数15.000人超の圧倒的な実績! | |
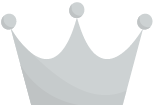 | 24.000円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・累計利用者数5.000人突破! |
|
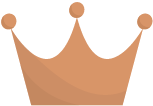  | 着手金55.000円 + オプション費用 LINE無料相談 | 弁護士 | ・有給消化・残業代・退職金未払い給与の請求&交渉ができる! |
|
 | 29.800円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・全国対応
| |
 代行 | 正社員26.800円 パート19.800円 LINE無料相談 クレジットカードOK | 労働組合 | ・創業16年 | |
 わたし NEXT | 正社員29.800円 パート19.800円 LINE無料相談 クレジットカードOK | 労働組合 | ・創業16年 |
|
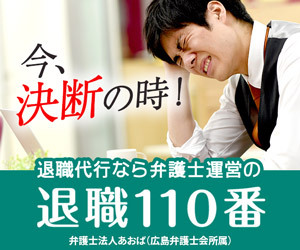 | 43.800円 + オプション費用クレジットカードOK | 弁護士 | ・全国対応 |
|
 | 27.000円 LINE無料相談
| 労働組合 | ・全国対応・24時間対応 |
|
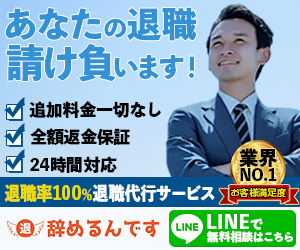 | 27.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・累計利用者数7.000人 |
|
 退職代行 退職代行オイトマ | 24.000円 LINE無料相談
| 労働組合 | ・24時間対応・365日対応 |
|
 ニコイチ | 27.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・弁護士監修
|
|
 | 25.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・全国対応 |
|
 RITRY RITRYリトライ | 25.000円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・会社と交渉可能 |
|
 ヒッター | 25.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・全国対応 |
|
 J-NEXT | 20.000円 LINE無料相談 | 一般企業 | ・24時間対応 |
|
 モームリ | 正社員22.000円 バイト12.000円 LINE無料相談 クレジットカードOK | 一般企業 | ・弁護士監修 |
|
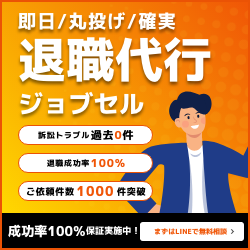 ジョブセル | 25.000円 LINE無料相談 | 一般企業 | ・累計相談数1.000件突破 |
|