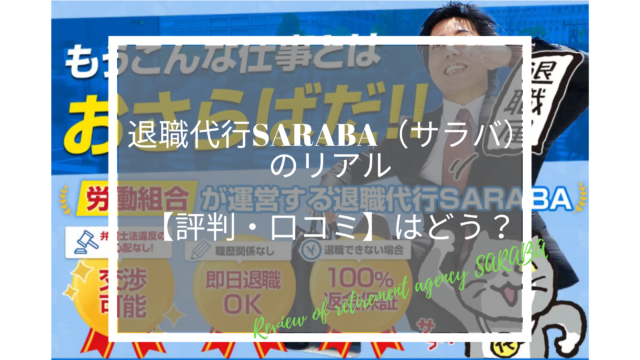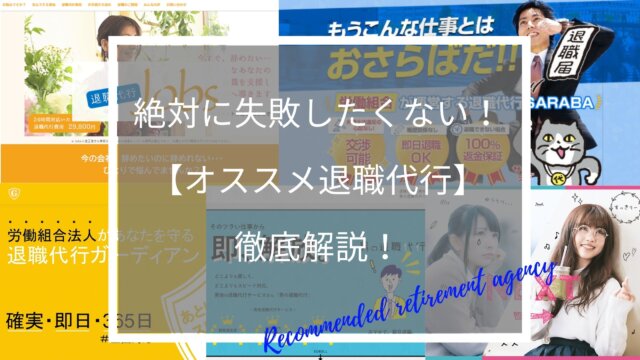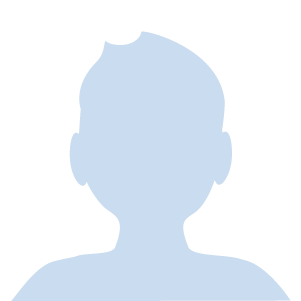退職代行サービス利用時の「退職届」「有給休暇の消化」「業務引継ぎ」等の対応方法【詳しく解説】
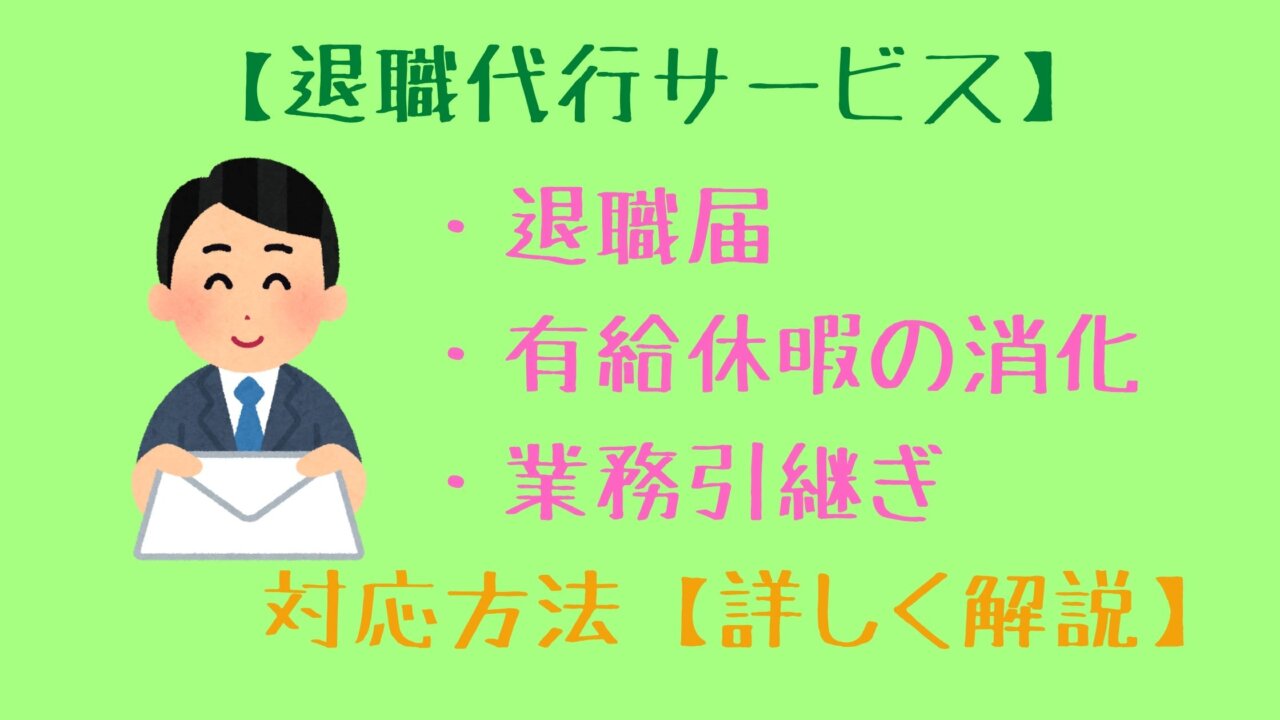
実際に退職代行サービスを利用した時の具体的な対応方法についてくわしく知りたい人
この記事を読むことで、 「退職届の提出・有給休暇の消化・未払い給与の請求・退職金の請求」 の対応方法と、 「業務の引き継ぎ・会社からの貸し出し物の返却・離職票の受け取り」 等の具体的な退職手続きの対応方法がわかります。
退職代行サービス利用時の「退職届」「有給休暇」「未払い給与・退職金の請求」の対応方法
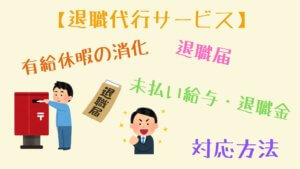 「退職届」「有給休暇」「未払い給与・退職金の請求」の対応方法について、順番に解説していきます。
「退職届」「有給休暇」「未払い給与・退職金の請求」の対応方法について、順番に解説していきます。未払い賃金とは
未払い賃金とは、あらかじめ定められている賃金が約束の支払日に支払われなかったものであり、「退職金・給与・賞与・休業手当」などのことです。「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスを利用して対応する
「一般企業」の退職代行サービスのできることは、あくまでも「退職の意思を伝える」ということです。 有給休暇の消化についても、「本人が有給休暇の消化については○○したいという意向があります」と伝えることはできます。 ですが、会社側が本人の希望を拒否した場合や、調整を望んでいる場合は、それ以上の交渉は「一般企業」の退職代行サービスではすることができません。一般企業の退職代行サービスではなく、弁護士又は労働組合運営の退職代行サービスを利用する。
会社側に有給休暇の請求・有給休暇の交渉ができるのは、「弁護士」または「労働組合運営」の退職代行サービスです。会社側が本人の希望を拒否した場合や、調整を望んでいる場合で、会社側と交渉が必要な場合は、「弁護士」または「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼するようにしましょう。退職金の請求について
就業規則を確認する
退職金については、「就業規則」や「雇用契約の内容」に従って支払われます。 なので、退職金を請求する前に、「就業規則」と「雇用契約の内容」をしっかりと確認しましょう。 交渉・代理請求は弁護士又は労働組合運営の退職代行サービスが対応 有給休暇の取得の時と同様に、「退職金の請求」などの退職に伴う交渉は「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスが対応できます。退職代行サービス利用時の「業務の引継ぎ」「会社からの貸し出し物の返却」「離職票の受け取り」の対応方法
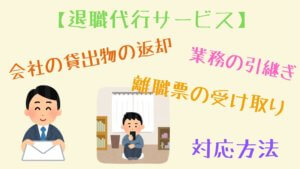
3-1「業務の引継ぎ」の対応方法
引き継ぎをすることは、民法や労働基準法で決められた義務ではない
引き継ぎをすることは、民法や労働基準法で決められた義務ではありません。 状況次第ですが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能です。- 引継ぎをしないことで、会社に具体的な損害がない場合は引継ぎはいりません。
- 引継ぎをしないことで、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの損害が出る場合は、引継ぎが必要です。
「業務引き継ぎ書」を作成し、郵送する
会社を退職する際に、会社側から、「最低でも引継ぎはしてほしいし、一度会社へ来てほしい」と主張してくることがあるかもしれません。 そのような場合は、必ず会社に行って引き継ぎをしなければいけないというわけではありません。 例えば、仕事のストレスが原因で体調不良となって退職する場合、そのようなことを言われても、体調が悪いのですから、行けるわけがありません。 ましてやそのストレスとなるパワハラ上司がいる場合はなおさらです。 そのような場合は、退職代行サービスを通じて、会社側に、3-2「会社からの貸し出し物の返却」の対応方法
返却物は本人から会社へ郵送で対応できる
ユニフォーム・パソコン・保険証等会社への返却物は、退職届と同様に、本人から会社へ郵送で返却すれば大丈夫です。できれば、退職日前に会社に置いてきたほうが、返却する手間が省けます。直接会社に渡しに行く必要はない
後日会社に直接渡しに行く必要はないので、安心してください。3-3「離職票の受け取り」の対応方法
離職票は会社から後日郵送で送られてくる
通常、離職票・雇用保険被保険者証等は会社から後日郵送で送られてきますので、大丈夫です。 退職代行サービス会社からも会社へ「本人へ郵送」するように伝えてくれます。会社に行く必要はない
本人が会社に行って、離職票を受け取る必要はないので、安心してください。退職代行サービス利用についての2つの質問
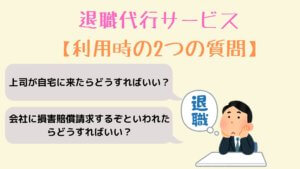
質問1:会社から電話がかかってくる・自宅に来る場合
質問2:会社から「損害賠償請求をする」と言われた場合
- 会社から損害賠償を請求すると言われました。どうすればいいのですか?
損害賠償請求の実際の考え方
「訴えるぞ!」は、ほとんどは脅し
会社側からの「訴えるぞ!」というのは、多くの場合は従業員に対する脅しです。実際に行動に移して裁判までする会社はほとんどありません。損害賠償には多大な費用と労力がかかる
なぜなら、会社が従業員に損害賠償するとなると、多大な費用と労力がかかるからです。 しかも、費用と労力がかかったからといって、必ず損害賠償請求額が会社の手に入るというわけではありません。損害賠償請求のメリットはあるのか?
冷静になって考えれば、裁判にかかる時間・費用を考えると、1人の社員の退職に対して、損害賠償を請求することは無駄でしかないといえます。損害賠償を請求された時の対応方法
会社側から損害賠償請求をされた時の対応は、まずは「会社側と交渉」をして、それでも解決しない時は「会社側と裁判で戦う」ということになるでしょう。「弁護士」「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼しておくのが良い
万が一、退職した時に会社側から訴えられた場合の対応を考えると、あらかじめ「会社との交渉」の対応をしてくれる、「弁護士」か「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼しておいた方が良いといえます。 そうすることで、万が一の時の交渉等の対応もしてもらうことができるので、安心です。まとめ
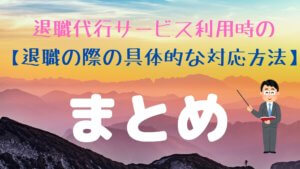 ここまで、「退職届の提出・有給休暇の消化・未払い給与の請求・退職金の請求」
の対応方法と、 「業務の引き継ぎ・会社からの貸し出し物の返却・離職票の受け取り」
等の具体的な退職手続きの対応方法について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? もう一度、要点をおさらいすると、
ここまで、「退職届の提出・有給休暇の消化・未払い給与の請求・退職金の請求」
の対応方法と、 「業務の引き継ぎ・会社からの貸し出し物の返却・離職票の受け取り」
等の具体的な退職手続きの対応方法について、詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか? もう一度、要点をおさらいすると、「退職届・有給休暇・未払い給与・退職金請求」の対応まとめ
- 「退職届」は会社に郵送で提出します
- 「有給休暇の消化」の交渉は「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスでしてもらえる。会社側に意向を伝えるだけなら「一般企業」の退職代行サービスでOK
- 「未払い給与・退職金請求」は、「就業規則」と「雇用契約の内容」をしっかりと確認し、交渉は「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスでしてもらえる。会社側に意向を伝えるだけなら「一般企業」の退職代行サービスでOK
業務引継ぎ・会社の貸出物返却・離職票の対応まとめ
- 「業務の引継ぎ」は。会社に行きたくない場合は、「業務引き継ぎ書」という形で引継ぎ内容についてできる範囲で・A4用紙1枚程度で内容をまとめて作成して提出する
- 「会社からの貸出物の返却」は、本人から会社へ郵送で返却すれば大丈夫。その旨を退職代行サービスが会社に伝えてくれる。
- 「離職票」は、会社から後日郵送で送られてくるので、大丈夫
「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼すべき2つの理由
退職代行サービスには「一般企業」「弁護士」「労働組合運営」の3種類がありますが、では、どの退職代行サービスに依頼するのが一番良いのでしょうか?会社側から反撃されるリスク
「一般企業」の退職代行サービスは、本人の意思を伝えるだけ
一般企業の退職代行サービスは、本人の意思を伝えることしかできません。 つまり、「退職の意思を伝えるだけ」「有給休暇消化の意思を伝えるだけ」となります。 会社側に反撃された際の交渉はできませんし、賃金などの代理請求をsることもできないのです。交渉・代理請求ができる「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスが安心
会社側から反撃されるリスクを考えると、「弁護士」又は「労働組合運営」の退職代行サービスへ依頼するのが安心と言えます。 万が一の時には代わりに「交渉」の対応をしてくれるからです。退職代行サービス利用者の金銭的負担
退職代行サービスの利用には、費用がかかります。 利用する側としては、できるだけ費用・出費は抑えたいところですよね。弁護士の退職代行サービスは費用が比較的高い
弁護士の退職代行サービスは費用が比較的高く、場合によっては10万円を超える時もあります。 なので、できるだけ費用を抑えたいという方には、おすすめできません。労働組合が運営する退職代行サービスに依頼するのがベスト
利用者の費用負担を考えると、一律30.000円前後と「低費用」で、しかも「交渉」も対応してくれる「労働組合が運営する退職代行サービス」に依頼するのが一番いい選択といえます。 「一般企業」と「弁護士」の退職代行サービスの両者の良いとこどりということですね。
退職代行SARABA
- LINE相談可
- 即日退職可
- 労働組合運営
- 「一般の退職代行」と違って、会社と交渉可
- 万が一、退職できなければ返金保証付きで安心
- 24時間365日いつでも無料相談OK
- メディア掲載多数
- 特典1:行政書士監修 退職届プレゼント
- 特典2:成功率98%・有給消化サポートあり
- 無料転職サポート付
- 退職成功率ほぼ100%
- 料金:一律24.000円
\料金:一律24.000円!返金保証付で安心!/

【即活用できる!即日退職!】
<退職代行17社 徹底比較表!>
※スマホは横画面でご覧ください。
| サービス | 価格(税込) | 運営法人 | 特徴 | |
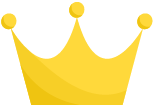  退職代行 退職代行SARABA | 24.000円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・累計利用者数15.000人超の圧倒的な実績! | |
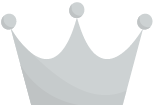 | 24.000円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・累計利用者数5.000人突破! |
|
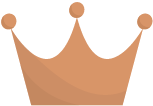  | 着手金55.000円 + オプション費用 LINE無料相談 | 弁護士 | ・有給消化・残業代・退職金未払い給与の請求&交渉ができる! |
|
 | 29.800円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・全国対応
| |
 代行 | 正社員26.800円 パート19.800円 LINE無料相談 クレジットカードOK | 労働組合 | ・創業16年 | |
 わたし NEXT | 正社員29.800円 パート19.800円 LINE無料相談 クレジットカードOK | 労働組合 | ・創業16年 |
|
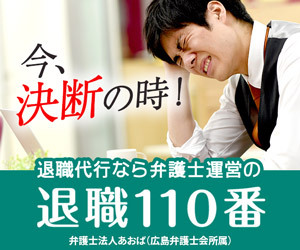 | 43.800円 + オプション費用クレジットカードOK | 弁護士 | ・全国対応 |
|
 | 27.000円 LINE無料相談
| 労働組合 | ・全国対応・24時間対応 |
|
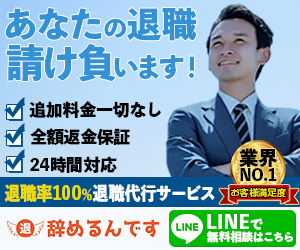 | 27.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・累計利用者数7.000人 |
|
 退職代行 退職代行オイトマ | 24.000円 LINE無料相談
| 労働組合 | ・24時間対応・365日対応 |
|
 ニコイチ | 27.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・弁護士監修
|
|
 | 25.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・全国対応 |
|
 RITRY RITRYリトライ | 25.000円 LINE無料相談 | 労働組合 | ・会社と交渉可能 |
|
 ヒッター | 25.000円 LINE無料相談
| 一般企業 | ・全国対応 |
|
 J-NEXT | 20.000円 LINE無料相談 | 一般企業 | ・24時間対応 |
|
 モームリ | 正社員22.000円 バイト12.000円 LINE無料相談 クレジットカードOK | 一般企業 | ・弁護士監修 |
|
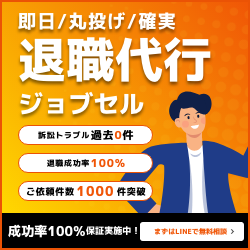 ジョブセル | 25.000円 LINE無料相談 | 一般企業 | ・累計相談数1.000件突破 |
|